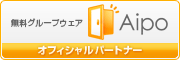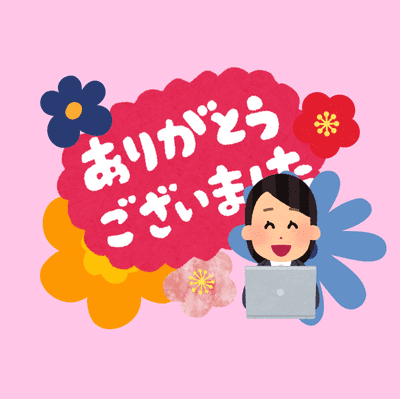二度目まして!ところで干支ってなんだろう?
2021-01-22
ご無沙汰しております!古川です!
年が明けてから半月以上経っており、時間の進む速さに驚いております。
皆様はどのように正月を過ごしましたでしょうか?
私はお節を食べていた記憶しか残っていません!(笑)
特に好きなのが黒豆とかまぼこ。決してこの時期にしか食べることが出来ないというわけでもないのですが、色とりどりで目でも楽しむことが出来るお節となると、いつにも増して美味しく感じてしまい、箸が止まりませんでした。
先日食べたばかりではありますが、来年のお節が待ち遠しいです!(笑)
さて、急に話が変わりますが、この正月にふと気になったことがありました。
タイトルにしましたが、「干支ってなんだろう?」です。
私にとって、生まれ年、年賀はがきのデザイン、性格診断、運勢占いというのが干支のイメージでした。
後は「丑三つ時」等の時間に関わりがあること、干支の順番を決めた競走の物語を聞いたことがある程度で、干支のルーツ等の歴史的な事柄については何も知らないことに気が付きました。
そんなこんなで、正月休みに干支について調べてみようとプログラミング言語の本(汗)と一緒に武光誠『日本人にとって干支とは何か』(株式会社河出書房新社、2020)を買いました。
こちらを読んで色々学ぶことができたので少し紹介したいと思います。
①いつ出来たのか?
A. 干支の起源は起源前16世紀~前11世紀頃に作られたもの
殷がいつ時代だったのか知らなかったので、予想以上に古くから存在していたことを知って驚きました。
②どういうものだったのか?
A. 干支は日付、十二支は方角。陰陽五行説的性質が強く、甲骨文字にも様々な意味や性質が込められていた。
干支で運勢占いや性格診断を行える理由はこれだったようです。また、どうして時間や方角と動物が結びついたのかずっと不思議に感じていましたが、背景に文字の存在があったことを知って、改めて文字の奥深さを実感しました。
③どのように変化してきたのか?
A. 上記で記載した様に、日付や方角など細分化していたものが時間と共に一つになった。
現代日本の干支とはかなり異なっていました。干支と十二支が異なるものということを知らなかったので新たな発見でした。
また、国ごとに思想や信仰の結びつき方が異なっているため動物も違うらしいです(インドはガルダなど)。
年が明けてから半月以上経っており、時間の進む速さに驚いております。
皆様はどのように正月を過ごしましたでしょうか?
私はお節を食べていた記憶しか残っていません!(笑)
特に好きなのが黒豆とかまぼこ。決してこの時期にしか食べることが出来ないというわけでもないのですが、色とりどりで目でも楽しむことが出来るお節となると、いつにも増して美味しく感じてしまい、箸が止まりませんでした。
先日食べたばかりではありますが、来年のお節が待ち遠しいです!(笑)
さて、急に話が変わりますが、この正月にふと気になったことがありました。
タイトルにしましたが、「干支ってなんだろう?」です。
私にとって、生まれ年、年賀はがきのデザイン、性格診断、運勢占いというのが干支のイメージでした。
後は「丑三つ時」等の時間に関わりがあること、干支の順番を決めた競走の物語を聞いたことがある程度で、干支のルーツ等の歴史的な事柄については何も知らないことに気が付きました。
そんなこんなで、正月休みに干支について調べてみようとプログラミング言語の本(汗)と一緒に武光誠『日本人にとって干支とは何か』(株式会社河出書房新社、2020)を買いました。
こちらを読んで色々学ぶことができたので少し紹介したいと思います。
①いつ出来たのか?
A. 干支の起源は起源前16世紀~前11世紀頃に作られたもの
殷がいつ時代だったのか知らなかったので、予想以上に古くから存在していたことを知って驚きました。
②どういうものだったのか?
A. 干支は日付、十二支は方角。陰陽五行説的性質が強く、甲骨文字にも様々な意味や性質が込められていた。
干支で運勢占いや性格診断を行える理由はこれだったようです。また、どうして時間や方角と動物が結びついたのかずっと不思議に感じていましたが、背景に文字の存在があったことを知って、改めて文字の奥深さを実感しました。
③どのように変化してきたのか?
A. 上記で記載した様に、日付や方角など細分化していたものが時間と共に一つになった。
現代日本の干支とはかなり異なっていました。干支と十二支が異なるものということを知らなかったので新たな発見でした。
また、国ごとに思想や信仰の結びつき方が異なっているため動物も違うらしいです(インドはガルダなど)。
簡単で、基本的なものだけ紹介させていただきました。その話聞いたことある!と感じるものも多いのですが、
「何故なのか?」まで詳しく説明・考察されていたのでとても面白かったです。
しっかりと日本と海外の違う部分にも焦点が当てられていて、日本人の性格が見えてくるのが特に良かったと思います。
本当に面白いので、興味を持った方がいたら是非読んでみてください。
それでは、また次回お会いしましょう!
「何故なのか?」まで詳しく説明・考察されていたのでとても面白かったです。
しっかりと日本と海外の違う部分にも焦点が当てられていて、日本人の性格が見えてくるのが特に良かったと思います。
本当に面白いので、興味を持った方がいたら是非読んでみてください。
それでは、また次回お会いしましょう!